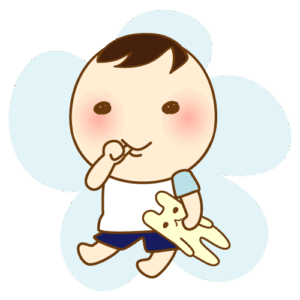こんにちは!
【浜松市 青木歯科医院】小児歯科担当の歯科衛生士です。
お子さんに初めての歯が生えてきた喜びとともに、「歯のケアって、いつから、どう始めたらいいの?」と不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
乳幼児期の丁寧なケアは、虫歯を防ぐだけでなく、お子さんが将来自分の歯の健康を守るための最も大切な土台作りになります。
実は、歯みがきには虫歯予防以外にも、こんなにたくさんの価値があるんです。
-
お口の機能の発達を促す(舌の正しい動きや噛む習慣につながる)
-
全身の健康を維持する(感染症リスクの低下や口呼吸の早期発見)
-
親子の絆を深める(毎日の大切なスキンシップの時間になる)
このガイドでは、0歳から5歳まで、お子さんの成長に合わせたケアのポイントを年齢別に解説します。
歯の価値は1本100万円ともいわれています!
一緒に、お子さんの一生の宝物になる健康な歯を育てていきましょう!!
【0歳】歯みがきデビュー!まずは「慣れる」から始めよう
🎯 この時期の目標: 口の周りに触れられることや歯ブラシの刺激に慣れる
「歯が1本でも生えてきたら」それが歯みがきスタートの合図です。乳歯の虫歯は、永久歯の歯並びに悪影響を及ぼすことも。最初の1本からケアを始めましょう。
💡 具体的な進め方 大切なのは「みがく」ことより「慣れる」こと。遊びの延長で進めましょう。
-
ステップ1:スキンシップで準備
まずは口の周りを指で優しく触れることから。リラックスさせてあげましょう。
-
ステップ2:姿勢に慣れる
保護者のひざの上に前向きに抱っこし、仕上げみがきの基本姿勢に慣れさせます。
-
ステップ3:歯ブラシを使ってみる
仕上げみがき用歯ブラシ(コンパクトヘッド・やわらかい毛)を使います。「少しみがいては、パッと取り出す」を繰り返し、笑顔で行うのがコツです。
🔑 仕上げみがきの重要ポイント
-
注意する場所: みがき残しやすい「上の前歯」を優先的に。
-
痛がらせない工夫: 上の前歯の真ん中にある筋(上唇小帯)に歯ブラシが当たると痛がります。保護者の指でそっとガードしてあげましょう。
-
歯みがき剤: フッ化物配合歯みがき剤がおすすめです。うがいができないので、最後は湿らせたガーゼなどで拭き取ります。
歯科衛生士から: この時期は「歯みがきって楽しいな」というポジティブな印象を与えることが一番大切です。
【1歳】自分でやりたい!気持ちを育てながら仕上げはしっかりと
🎯 この時期の目標: 子ども自身が歯ブラシを持つ練習を始める
奥歯が生え始め、食べ物の種類が増えるため、虫歯リスクが高まる時期です。
💡 「自分みがき」の始め方 スプーンを自分で持てるようになったら、子ども用歯ブラシを持たせてみましょう。
まずは口に入れる練習から。保護者の方が楽しそうに一緒にみがく姿を見せるのも効果的です。(※必ず保護者の方が見守ってください)
🔑 保護者の仕上げみがきの進化点
-
最重要ポイント: 1日1回以上、特に就寝前の仕上げみがきが大切です。(睡眠中は唾液が減り、虫歯菌が活動しやすいため)
-
優先してみがく場所:
-
上の前歯の表側
-
奥歯の溝があるかみ合わせの面
-
-
新しいツール: 奥歯が生えたら、歯と歯の間のケアも必要です。初心者でも使いやすい「ホルダータイプのデンタルフロス」を導入しましょう。
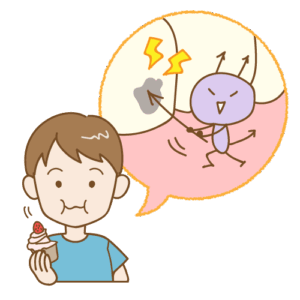
✅ 1歳6ヶ月児健診の頃:生活習慣チェック
-
哺乳瓶でジュースなどを飲んでいませんか?
-
食事や間食の時間は決まっていますか?(ダラダラ食べはNG)
-
保護者の虫歯菌がお子さんにうつる可能性も。保護者自身のお口の健康も大切です。
【2歳】「いやいや期」の歯みがき攻略法
🎯 この時期の目標: いやいや期を乗り越え、歯みがきを習慣化する
自我が芽生え、歯みがきを断固拒否!でも、この時期は虫歯リスクがさらに高まります。
😫 虫歯リスクが高い3大スポット
-
上の前歯
-
歯と歯の間
-
奥歯のかみ合わせの面
💡 「いやいや期」を乗り切るアイデア 無理強いは禁物です。楽しい工夫を取り入れましょう。
-
遊びに変える: 「歯ブラシ電車が出発しまーす!」「怪獣さんの口の中をきれいにしよう!」
-
真似っこさせる: 保護者が楽しそうにみがく姿を見せて誘う。
-
習慣の力を使う: 食事やお風呂と同じように、できるだけ同じ時間・同じ場所で行い、生活リズムに組み込む。
🔑 この時期のケアのポイント
-
歯ブラシの使い分け: お子さんは歯ブラシを噛みがち。汚れが落ちにくくなるため、子どもが使う「自分みがき用」と、保護者が使う「仕上げみがき用」は分けるのがおすすめです。
-
うがいの練習: コップで水を口に含めるようになったら、「ぶくぶくうがい」の練習を始めましょう。
歯科衛生士から: 目標を「1日1回、寝る前だけでもしっかり仕上げみがきができればOK」に設定すると、親子の気持ちが楽になりますよ。
【3歳】親子で協力!「きれいにする」意識を育てよう
🎯 この時期の目標: 「歯をきれいにする」という目的を理解し、本格的なブラッシング練習を始める
乳歯がすべて生えそろう時期です。言葉の理解も進み、歯みがきの意味がわかるようになります。
💡 親子で進める「共同作業」
-
役割分担: まず子どもが「自分みがき」→ その後で保護者が「仕上げみがき」で総仕上げ。この流れを習慣にしましょう。
-
仕上げみがきのポイント: 引き続き、虫歯になりやすい3大スポット(上の前歯、歯と歯の間、奥歯)を優先的に。特に一番奥の歯は要注意。デンタルフロスも使いましょう。
-
歯みがき剤の使い方: ぶくぶくうがいが上手にできるようになったら、フッ化物配合歯みがき剤を本格的に使用。すすぎは少量の水(大さじ1杯程度)で1回だけにすると、フッ素の効果が高まります。
✅ お口の機能もチェック 乳歯が生えそろったら、お口全体の機能にも目を向けましょう。
-
食事の時、よく噛んでいますか?
-
お口をぽかんと開けていませんか?(口呼吸の可能性)
-
指しゃぶりの癖は続いていませんか? 気になることがあれば、歯科健診などで気軽に相談してください。

【4~5歳】自分みがきをレベルアップ!永久歯を迎えよう
🎯 この時期の目標: 臼歯(奥歯)のかみ合わせの面と頬側を自分でみがけるようになる
6歳頃から、いよいよ一生使い続ける永久歯が生え始めます。この大切な歯を万全の状態で迎えるため、乳歯のケアが非常に重要です。
💡 子どもに教える「みがき方のコツ」 お子さんにも分かる言葉で、正しいみがき方を教えてあげましょう。
-
歯にまっすぐ当てる: 歯ブラシの持ち方を「こんにちは持ち」「さようなら持ち」と教えてあげましょう。
-
小さく動かす: 「大きい『ぞうさんみがき』じゃなくて、小さい『ありさんみがき』でやってみよう」
-
軽い力でみがく: 歯ブラシの毛先が開かないくらいの優しい力で。
🔑 保護者の役割の変化 お子さんのレベルが上がっても、保護者の役割はまだまだ重要です。
-
仕上げみがきは継続: 子ども一人で完璧にみがけるのは9〜10歳頃から。毎晩必ず保護者が仕上げみがきをしましょう。
-
確認と指導: お子さんがみがいた後、「どこがピカピカになったかな?」と確認し、みがき残しを教えます。
-
やる気を引き出す声かけ: 「奥歯まで自分でできたね!」と、できたことを具体的に褒めてあげることが、お子さんの自立心につながります。

困ったときのQ&A:よくある質問
Q1. 子どもが歯ぎしりをします。大丈夫でしょうか?
A1. お子さんの歯ぎしりの多くは、かみ合わせを調整するための一時的なもので、年齢と共に自然になくなることがほとんどです。
ただし、歯が極端にすり減っている、あごを痛がるなどの症状があれば、小児歯科で相談してください。
Q2. 指しゃぶりは、いつまでにやめさせるべきですか?
A2. 3歳頃までは自然な行為なので、無理にやめさせる必要はありません。4歳以降も頻繁に続く場合は、歯並びへの影響も考えられるため、専門家への相談を検討しましょう。
Q3. おしゃぶりは、いつまでにやめるべきですか?
A3. 奥歯が生えてくる1歳半頃からやめる準備を始め、2歳過ぎには卒業できるのが望ましいです。
長く使い続けると、歯並びやかみ合わせに影響が出る可能性があります。
さいごに:親子で育む、一生の健康
乳幼児期の予防歯科は、保護者の方が主役です。
この時期に、保護者の方がお子さんのお口に丁寧に関わり、正しいケアを根気強く続けてあげることが、お子さんが将来自分の歯の健康を守る力への、何よりの贈り物になります。
毎日の歯みがきは大変に感じることもあるかもしれませんが、それはお子さんの小さな成長を日々実感できる、かけがえのない時間でもあります。
ぜひ、このガイドを参考に、歯みがきタイムを親子の絆を深める楽しい習慣にしてくださいね。