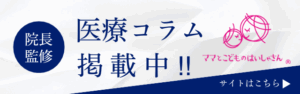はじめに:なぜ冬になると歯が痛くなるの?
浜松市の皆さま、こんにちは! 青木歯科医院 院長の青木です。
今日は急に寒くなりましたね。
つい暖房をいれてしましました!
急に気温が下がり、空気が乾燥する冬。
皆さまの中に、「寒い外に出た途端、歯に**ズキン!**とした痛みが走る」「冷たい水でうがいをすると、まるで神経に響くように沁みる」といった経験をされた方はいませんか?
多くの方が「冬はただでさえ寒いから」と我慢してしまいがちですが、その痛みは単なる寒さのせいではないかもしれません。
実は、冬の環境は歯にとって非常に過酷で、既存のトラブルを悪化させたり、新たな問題を引き起こしたりする原因が潜んでいます。
この記事では、寒い冬に歯が痛くなったり沁みたりする主な原因を、5つの理由に分けて詳しく解説します。
あなたの歯の痛みが「知覚過敏」なのか、「歯ぎしり」によるものなのか、それとも別の原因なのかを探り、今日からできる対策方法までご紹介します。
快適な冬を過ごすために、ご自身の歯と口の健康を見直すきっかけにしてください。

理由1:冬の寒さが引き起こす「知覚過敏」の悪化
冬の歯の痛みの代表格ともいえるのが、「知覚過敏」です。
知覚過敏とは、歯のエナメル質が何らかの原因で削れたり、歯茎が下がったりすることで、内部にある**象牙質(ぞうげしつ)**が露出し、その象牙質に「冷たい・熱い・酸っぱい」といった刺激が加わることで痛みを感じる状態を指します。
冬に知覚過敏が悪化するメカニズム
冬場は、単に気温が低いだけでなく、次の2つの理由で症状が悪化しやすくなります。
-
冷たい空気による直接的な刺激 口を開けたときや、マスクを外した瞬間に、キンキンに冷えた外気が象牙質に直撃します。この刺激が、歯の内部の神経(歯髄)に伝わり、「ズキン!」という鋭い痛みとなって現れるのです。
-
寒暖差による影響 暖かい室内から急に寒い外に出たとき、または寒い屋外で温かい飲み物を口にしたときなど、歯は急激な温度変化にさらされます。この大きな寒暖差は、歯の表面に目に見えないほどの微細なひび割れ(マイクロクラック)を生じさせ、象牙質の露出を招き、知覚過敏を悪化させる原因になります。
知覚過敏のセルフチェック
-
冷たい空気や水が触れたとき、一瞬だけ鋭く痛むが、刺激がなくなるとすぐに治まる。
-
虫歯の自覚はない。
-
特に歯の根元や、歯茎が下がっている部分が沁みやすい。
理由2:無意識のうちの「食いしばり・歯ぎしり」
「朝起きたら、なぜか奥歯や顎の周りが痛い」という方は、寒さによる食いしばりや歯ぎしりが原因かもしれません。
寒さと食いしばりの関係
寒いとき、人は無意識に体に力を入れて寒さに耐えようとします。このとき、奥歯を強く噛みしめる「食いしばり」が起こりやすくなります。特に就寝中は、寒さで体が緊張状態になり、無意識の歯ぎしり(ブラキシズム)や食いしばりが強くなる傾向があります。
歯ぎしりが引き起こす痛み
歯ぎしりや食いしばりは、歯に想像以上の強い力をかけます。
-
歯の痛み(筋肉痛): 噛むときに使う「咬筋(こうきん)」という筋肉が、夜間に長時間緊張することで筋肉痛を起こし、それが奥歯の痛みや顎の痛みとして感じられます。
-
歯の摩耗とヒビ: 強い力によってエナメル質がすり減り、象牙質が露出して知覚過敏が悪化します。また、歯に細かいヒビが入り(デンタルクラック)、そのヒビが寒暖差で刺激されることで、さらに激しい痛みを引き起こすことがあります。
知覚過敏と診断されてもなかなか治らない場合、根本原因が「食いしばり」にあるケースも少なくありません。
理由3:冬の乾燥による「口腔内の自浄作用の低下」
冬は空気が乾燥しており、それに伴いお口の中も乾燥しやすくなります。この「乾燥」も、歯の痛みを引き起こす大きな原因となります。
唾液の量が減るとどうなるか?
唾液には、食べかすを洗い流したり、酸を中和したりする**「自浄作用」と、歯のミネラルを補給して修復する「再石灰化作用」**があります。
冬の乾燥や、水分補給が減ることによって唾液の分泌量が低下すると、これらの重要な働きが弱くなります。
-
歯周病菌の繁殖: 自浄作用が低下することで、虫歯菌や歯周病菌が増殖しやすくなります。
-
歯茎の炎症の悪化: 歯周病が進行すると歯茎に炎症が起き、歯茎が下がって知覚過敏になりやすくなります。また、炎症している歯茎は血行不良によって痛みを強く感じやすくなります。
-
虫歯の進行: 再石灰化が追いつかず、小さな虫歯が一気に進行し、冷たい刺激が神経に達して強い痛み(虫歯性疼痛)として現れることがあります。
理由4:血行不良による「歯茎の痛み」と「免疫力の低下」
寒い冬は、体温を保つために血管が収縮し、全身の血行が悪くなりがちです。これは、お口の中の健康にも悪影響を及ぼします。
歯茎の血行不良と痛み
歯茎は毛細血管が非常に豊富で、血流に乗って酸素や栄養が送られ、老廃物が排出されています。
しかし、寒さで血行が悪くなると、歯茎の組織に必要な栄養が行き届かなくなり、歯茎の免疫力が低下します。
-
歯周病の悪化: 免疫力が低下することで、歯周病の炎症が進行しやすくなります。
-
歯茎の腫れ・出血: 炎症を起こしている歯茎は、血行不良によって腫れや痛みが強くなることがあります。
-
痛覚の変化: 寒さによる血管の収縮は、炎症部分の神経を刺激し、痛みを強く感じさせるという報告もあります。
理由5:古い詰め物・被せ物の「隙間」
冷たい刺激が特定の歯だけに「ズキッ」とくる場合、それは以前治療した歯の詰め物や被せ物(銀歯など)の劣化が原因かもしれません。
詰め物・被せ物の劣化が引き起こす問題
-
素材の収縮: 金属やプラスチックなどの詰め物・被せ物は、歯の天然の組織とは異なり、冬の寒さでわずかに収縮します。この収縮によって、歯と詰め物の間にごく小さな隙間が生じることがあります。
-
隙間からの刺激: その隙間に冷たい空気や水が入り込むと、歯の象牙質や神経に直接刺激が伝わり、痛みを感じます。
-
二次虫歯の発生: さらに、この隙間から細菌が侵入し、内部で二次的な虫歯が進行してしまうことがあります。二次虫歯は気づきにくく、痛みが出たときには神経に達していることも少なくありません。
もし特定の治療済みの歯だけが痛む場合は、詰め物の適合を歯科医院でチェックしてもらう必要があります。
寒い冬の歯の痛みを乗り切る!今日からできる対策
ご紹介した5つの理由から、冬の歯の痛みは「寒さ」だけでなく、「知覚過敏」「歯ぎしり」「乾燥」などが複合的に絡み合っていることが分かります。
ご自宅でできる具体的な対策を実践し、痛みを緩和しましょう。
1. 歯の冷えを防ぐ「口元ガード」
-
マスク・マフラーの活用: 外出時は、冷たい外気が直接歯に当たらないよう、必ずマスクやマフラーで口元を覆いましょう。
-
鼻呼吸の意識: 口で呼吸すると冷たい空気が直接歯に当たるため、意識して鼻で呼吸するように心がけましょう。
2. 知覚過敏専用歯磨き粉の活用
-
知覚過敏ケア成分配合のものを選ぶ: 硝酸カリウムなどの成分が、象牙質の穴(象牙細管)をふさぎ、神経への刺激をブロックして痛みを和らげます。
-
正しいブラッシング: 強く磨きすぎるとエナメル質を削り、歯茎を下げて知覚過敏を悪化させます。柔らかめの歯ブラシで優しく、ていねいに磨きましょう。
3. 食いしばり・歯ぎしり対策
-
「歯を離す」を意識: 日中に無意識に噛みしめていることに気づいたら、「力を抜く」「上下の歯を離す」ことを意識するクセをつけましょう。
-
歯科医院での相談: 就寝中の歯ぎしりが疑われる場合は、歯科医院でカスタムメイドの**マウスピース(ナイトガード)**を作成することをおすすめします。
歯への負担を大幅に軽減できます。
4. 口腔内の乾燥対策
-
こまめな水分補給: 冬は乾燥しているため、意識的に水やお茶で水分を補給し、お口の中を潤しましょう。
-
唾液腺マッサージ: 顎の下や耳の下にある唾液腺を優しくマッサージすることで、唾液の分泌を促しましょう。
5. 歯の定期検診とプロのクリーニング
最も重要なのは、**「痛みの原因を見つけること」**です。
ご自身では知覚過敏だと思っていても、実は進行した虫歯や歯周病、詰め物の劣化が原因かもしれません。
-
精密な診断: 浜松市の青木歯科医院では、歯の痛みの根本原因を正確に診断します。
-
知覚過敏の専門治療: 薬液を塗布して象牙質の露出部分を保護する処置や、レーザー治療など、症状に合わせた専門的な治療をご提案できます。
-
プロのクリーニング: 歯石やプラークを除去し、歯周病の悪化を防ぎ、歯茎の健康を回復させます。
おわりに
冬の歯の痛みは、「寒さのせい」と片付けずに、お口からのSOSだと受け止めることが大切です。
「ズキン!」とした痛みを我慢せず、まずはご自身の症状がどの理由に当てはまるかチェックしてみてください。そして、少しでも不安を感じたら、迷わず青木歯科医院にご相談ください。
私たちは、皆さまが寒い冬を快適に、そして健康な歯で過ごせるよう、全力でサポートいたします。お気軽にご来院ください。
浜松市の歯の健康は、青木歯科医院にお任せください。